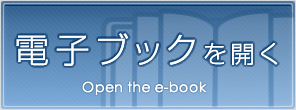Fのさかな20号 虎魚(おこぜ) 2011年 夏 page 18/40
このページは fsakana20 の電子ブックに掲載されている18ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
能登半島のおさかな情報誌
能登平家物語健礼門院に別れを告げた時忠は、北陸道を経て能登へと旅立ちましたが、流罪となっても油断のならない人物として警戒していたのか頼朝の命により、かつて以仁王に仕えていた長兵衛尉こと長谷部信連が、珠洲郡に接する大屋荘(石川県鳳珠郡)の地頭に任じられていました。能登で暮らすことわずか4年ばかり、赦免の日を待ちわびながら、かつて「平家にあらずんば」と豪語した時忠は石川県珠洲市大谷町で六十有余歳の生涯を閉じたのでした。訃報に接した頼朝は「智臣の誉れにより先帝(安徳天皇)の御代、平家が世にあるとき諸事を補佐した。いまでも朝廷にとって惜しい人であったろう」と述べたといわれます。時忠末裔伝承伝承では、時忠の上陸地は珠洲市馬緤町。神武天皇が熊野から橿原に導いた八咫烏の話を想定させるように、時忠も守り刀「烏丸」の精である烏に導かれて珠洲市烏川河口付近の「則貞(大谷町)」に居を構えたと云われます。のちに「古屋(大谷町)」に移り住み、「大谷十二名」「馬緤七名」など名主クラスの多くが時忠や若山荘領日野家の末裔と伝えており、時忠末裔の則貞家屋敷の近くには昭和三十六年、時忠七百七十五回忌を記念して祖父が時忠の子孫と伝えられる歌人山口誓子が詠んだ歌碑が立ち、屋敷の一角には時忠主従の墓群が残りその中の一番大きな塔が、時忠のものと伝えられ、人目を憚るようにひっそりと眠っています。パイオニアだった時国家の活躍時忠の没後、子の時国が、実名の時国を姓として時国家を興し輪島の地に館を構えたといわれます。代々当主の努力によって困窮していた近隣の農村の救済を図り、豪農として長きにわたり繁栄しました。伝承では室町時代、水運に便利な河口近くに建てられた時国家の母屋の間口は約五十メートル、二百八十坪あまりの巨大な土地に土蔵、酒蔵、馬屋、稲蔵が建っていたことが発掘調査で明らかにされています。特に時国が「目」を向けたのは海でした。当時館の近くは、船の出入りが容易であったため、海での交易を重視し福原を築いた清盛と同様、常に海に関心を抱いたパイオニアで時忠の末裔はめざましい開拓魂をあらわに勇躍していきました。江戸時代初期の時国家の石高は三百石。下人の数は百五十人から二百人ほども抱えていたようで、広い田畑を耕作する他に、製塩、木炭、鍛冶、石切り、桶細工など幅広い業種を手掛けていたと考えられ上時国家(輪島市町野町)国指定重要文化財時忠一門の墓と伝えられる五輪塔群(珠洲市大谷町)ときくにけ Summer 2011 Fのさかな18